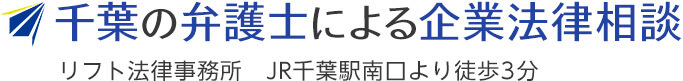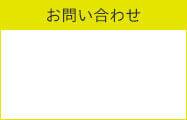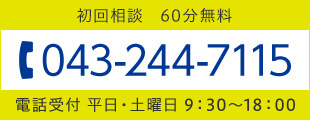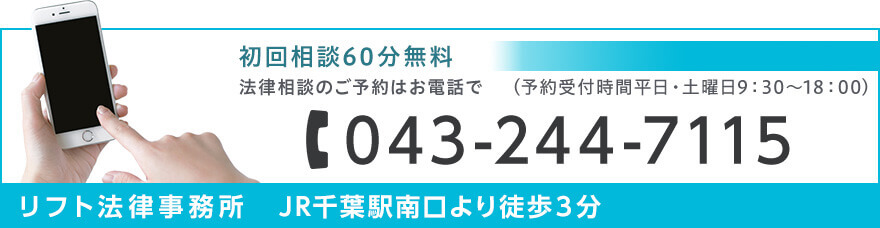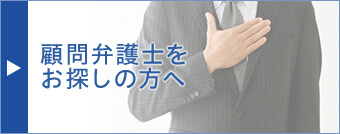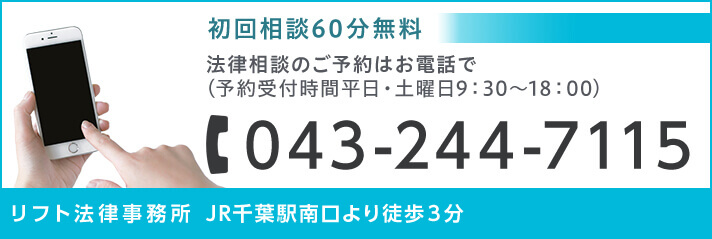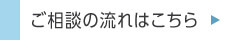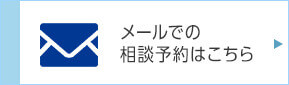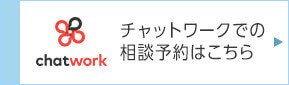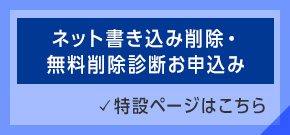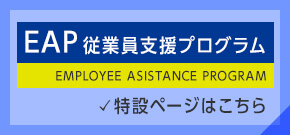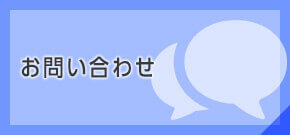インスタのステマ規制強化!景表法違反で企業が受ける罰則について弁護士が解説
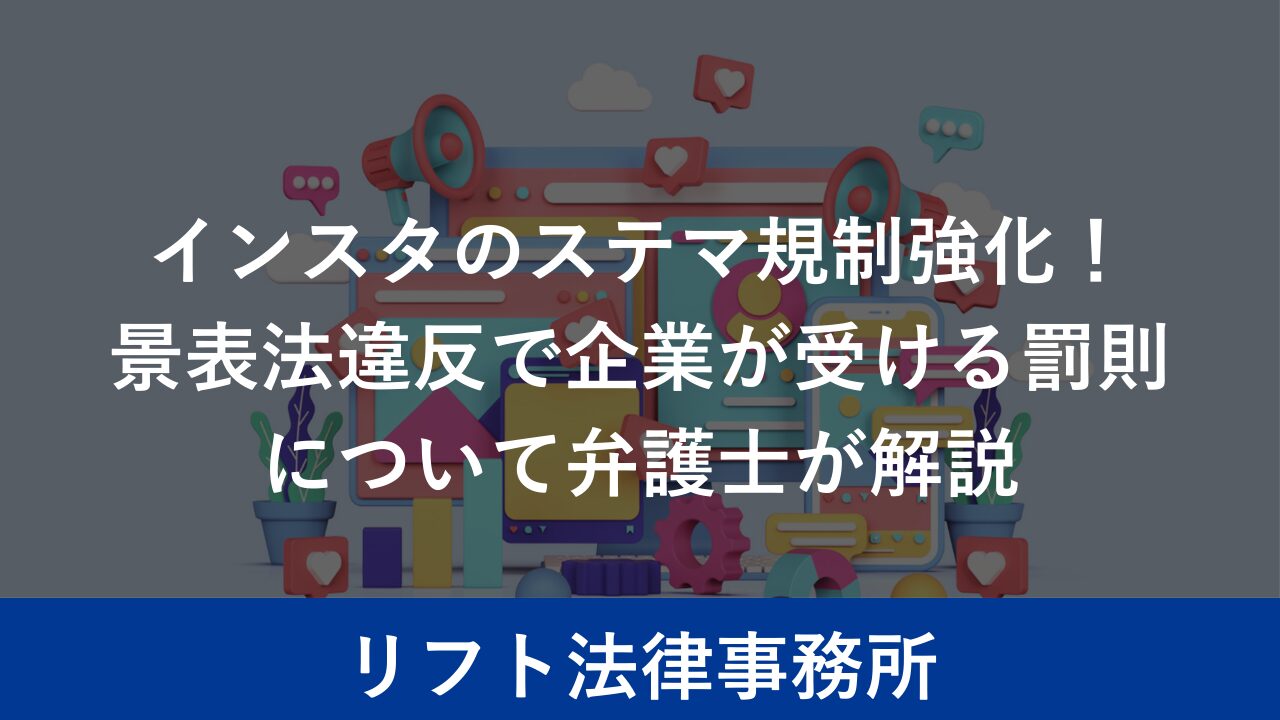
インスタでのステルスマーケティング(ステマ)規制が強化され、企業が景品表示法違反に問われるリスクが高まっています。
規制強化により、企業は「広告だと認識されない形」でのマーケティング活動を行えなくなります。
違反した場合、罰則を受ける可能性があるため、規制を遵守した方法でPR活動を行うことが重要です。
この記事では、ステマ規制とは何か、企業が受ける罰則や回避方法について解説します。
【目次】
ステマ規制とは
ステマ規制とは、広告であることを隠して行う宣伝行為を取り締まり、消費者が正確な情報をもとに商品やサービスを選べるようにするためのルールです。
そもそもステマは、個人の感想や口コミのように装うことで消費者の信頼を得て商品を売り込む手法です。
不透明な広告から消費者を守るため、2023年10月1日から景品表示法にもとづいて、不正な広告行為が厳しく取り締まられるようになりました。
ステマ規制に至った背景
消費者庁がステマ規制に乗り出した背景には、インターネット広告市場の急成長と、それにともなう消費者被害の拡大があります。
2021年、日本のインターネット広告費は約2兆7,052億円に達し、新聞・雑誌・ラジオ・テレビといったマスメディア4媒体の広告費合計である、約2兆4,538億円を上回りました。
その結果、インターネット広告は国内市場の中心的媒体となり、多くの消費者が日常的に触れる存在となっています。
インターネット広告は、従来の広告媒体と比べて表示スペースの制約が少なく、豊富な情報量を提供できる点が大きなメリットです。
しかし、その自由度の高さが、広告手法の不透明さや不正利用を招く要因にもなっています。
とくに、SNSやレビューサイトを活用した広告では、一般のユーザーの投稿や第三者の意見を装った手法が広がっているのが現状です。
広告であることを隠された広告は、情報の真偽を見分けることが極めて難しい状態での商品・サービス購入につながるおそれがあります。
具体的には、ステマによって「口コミで高評価」と信じて購入した商品が期待外れだったり、誇張されたレビューを信じて契約したサービスがトラブルの原因となったりするケースが増えています。
こうした状況は、金銭的な損失をもたらすだけでなく、精神的な負担や不信感を抱かせる要因となるでしょう。
消費者被害が増加するなか、消費者庁はステマが景品表示法の目的である「消費者の自主的かつ合理的な選択」を阻害する行為として、規制が開始されることが決定しました。
新たな規制の導入により、広告の透明性が確保され、消費者が信頼できる情報をもとに選択できる環境の整備が期待されています。同時に、企業にとっても、公平な市場競争の促進につながるとされています。
出典:「ステルスマーケティングに関する検討会 報告書(案)」消費者庁ウェブサイト
ステマ規制対象について
ステマ規制では、広告であることを消費者に分かりやすく示すことが義務付けられています。
事業者が発信する情報であるにもかかわらず、その情報が広告であると消費者が判断できない場合、不当表示として規制の対象となります。
具体的には以下が規制の対象です。
● SNS投稿
● ECサイトでのレビュー投稿
● テレビ などの広告全般
これらの行為が「中立的な意見やレビュー」として誤認されると、消費者の公正な選択を妨げる可能性があります。
そのため、事業者は「PR」や「広告」といった明確な表記を行い、消費者が発信者を正しく認識できるようにしなければなりません。
ステマに該当する具体的な事例
ここでは、ステマに該当する具体的な事例を紹介します。
一般消費者を装った投稿
商品にかかわる従業員が、あたかも自分が購入したかのように商品の写真や感想をSNSに投稿する手法です。
関係者が自分の立場を隠し、消費者として商品やサービスを紹介するため、広告だと気づかれにくいのが特徴です。
また、企業が自社の商品だけでなく、競合他社の商品に対して否定的な投稿も「なりすまし」と見なされます。
広告であることを隠した投稿
SNSやYouTubeなどのプラットフォームでは、インフルエンサーや有名人が持つ影響力が非常に強いため、個人的な意見や感想として受け入れやすく、結果として商品を購入する可能性が高まります。
しかし、後から宣伝であることが発覚すると、商品やサービスだけでなく、インフルエンサーの信用も失われるリスクがあります。そのため、インフルエンサーは、報酬を受け取った投稿であることを必ず明記しなければなりません。
内容を操作・誘導したキャンペーン投稿
企業が消費者に特定の商品について感想を投稿させる際、内容を指定したり、特定の特徴を含めるよう求めたりすると、ステマに該当します。
一方で、消費者が自分の意見で商品を使って感想を投稿した場合、ステマには該当しません。
ステマ規制の景表法違反で企業が受ける罰則
違反した企業は、2年以下の懲役または300万円以下の罰金、あるいはその両方が科せられます。
また、両罰規定にしたがって、法人に対しても最大3億円の罰金が科せられる場合があります。
なお、違反が確認された場合、まず消費者庁から措置命令が下されます。措置命令は、以下のような内容が一般的です。
・違法な広告をやめること
・消費者に違反の事実を知らせること
・今後同じことを繰り返さないための対策を取ること など
措置命令が出されると、その内容が公表されるため、企業の信頼性が大きく損なわれることになります。
たとえば、既存の顧客が離れたり、新たな取引先との契約が難しくなったりするなど、目に見えない形でビジネスチャンスを失うリスクもあります。結果的に、企業は罰則以上に大きな損害を被る可能性が高いといえるでしょう。
出典:「ステルスマーケティングに関する検討会 報告書(案)」 消費者庁ウェブサイト
インスタでステマ規制にならないための対策
インスタグラムでステマ規制を避けるためには、以下のポイントを守ることが重要です。
・投稿が広告であることを明示する
・タイアップ投稿ラベルを用いる
・誤解を招く情報を発信しない
まず、投稿が広告やプロモーションであることを、フォロワーに分かりやすく伝えることが基本です。
「#広告」や「#タイアップ」などのラベルを使用することで、フォロワーに対して透明性を保ち、誤解を防げます。
さらに、消費者を不必要に誘導するような内容や過度に誇張した表現を避けることも重要です。
なお、第三者に投稿を依頼する際も、3つのポイントを守ることで、違反するリスクを避け、信頼性の高いプロモーション活動を実現できます。
弁護士の必要性
ステマ規制を遵守するためには、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
なぜなら、規制の対象となるのは広告を出す企業であり、PRを依頼されたインフルエンサーではないためです。
ステマ規制に違反しないためには、規制の内容をしっかりと理解しなければなりません。
弁護士に依頼すれば、投稿前にリーガルチェックを受けられるため、違反のリスクを事前に回避できます。
また、過去に行った投稿が規制に該当していないか不安な場合も、弁護士に相談して適切な対応を求められます。
これにより、今後のPR活動を行う際にも安心して取り組めるだけでなく、万が一問題が発生した場合にも迅速に対応できるでしょう。
また、違反は投稿者にも大きな影響を与える可能性があります。とくに、ステマに対する消費者の反応は敏感です。
規制に違反した場合、企業から損害賠償請求を受けるリスクや、SNS上での炎上による社会的信用の失墜など、深刻な影響も考えられます。
そのため、企業だけでなく投稿者にとっても、弁護士への早期相談が推奨されます。
リフト法律事務所ができること
ステマ規制は、消費者が自分の意志で公平に商品やサービスを選べるように守るルールです。
広告を出す企業は、規制をしっかり理解し、自社の広告が規制に該当しないよう十分に注意する必要があります。
リスト法律事務所では、ステマ規制に対応するためのアドバイスをはじめ、デジタル広告に関するあらゆる法的サポートを提供しています。マーケティング活動が法律に違反していないか、ステマを指摘された場合の対策について不安な方は、お気軽にご相談ください。
▼関連記事はこちら▼
Instagramで誹謗中傷?悪質な書込みへの対応を弁護士が解説
弁護士 川村勝之
最新記事 by 弁護士 川村勝之 (全て見る)
- 【お知らせ】弁護士入所のお知らせ - 2025年4月3日
- 【メディア】『弁護士ドットコムニュース』に川村弁護士への取材記事が掲載されました - 2025年3月31日
- 【セミナー報告】川村弁護士が『法律事務所経営研究会』で「ペーパーレス・リモートワーク」をテーマに講師を務めました - 2025年2月4日