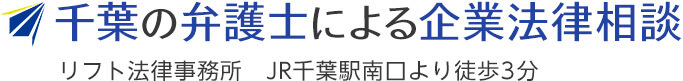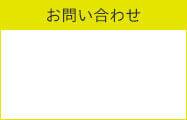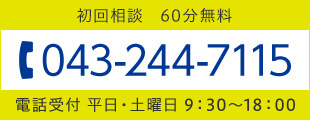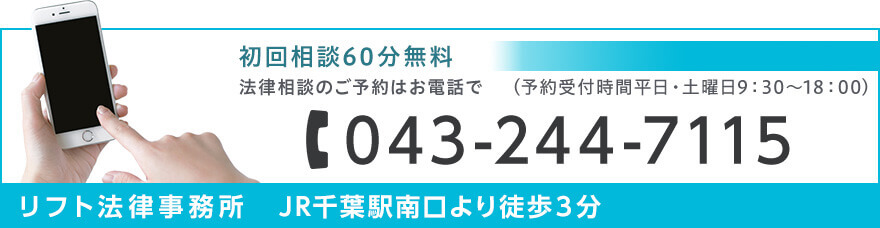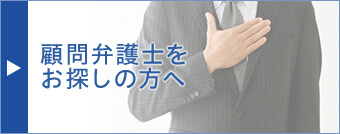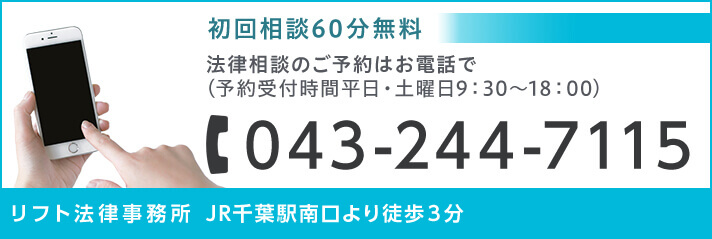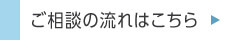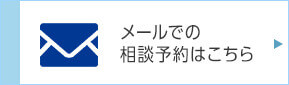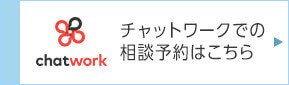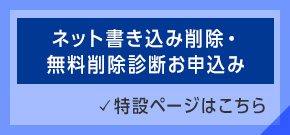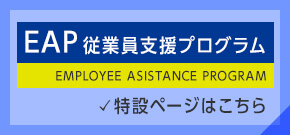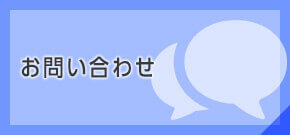ブライダル業界における著作権問題~結婚式での音楽利用~

結婚式の大切な瞬間を彩る音楽や映像ですが、知らず知らずのうちに著作権問題に直面するケースも少なくありません。
結婚式で使用される音楽や映像は、多くの場合、著作権で保護された作品です。そのため、無断で使用してしまうと、法的なトラブルや高額な賠償金を請求される可能性もあります。
この記事では、結婚式でよく使われる音楽や映像における著作権の基本的な知識をはじめ、具体的なリスクや対応方法を分かりやすく解説します。
【目次】 [hide]
結婚式と著作権の基本的な理解
音楽や映像には「著作権」という権利があります。
著作権は、作品を作った人の権利を守るための法律であり、多くの場合、作品を使うには作った人の許可が必要です。
また、音楽や映像を使う場合、著作権だけでなく「著作隣接権」や「支分権」など、関連するルールについて知っておくことが大切です。
▼関連記事はこちら▼
【ブライダル業者必見!】ブライダルと法律に関する押さえておきたいポイント3選と注意点を解説
【ブライダル業者必見!】婚礼写真に関する法律問題の注意点を弁護士が徹底解説
【弁護士が解説!】フォトウエディングの著作権で押さえるべき2つのポイント
【弁護士が解説】フォトウエディング・前撮りで法律に注意すべき3つのシチュエーション
フォトウエディング事業者になる前に知っておくべき基礎知識と市場規模
著作権・著作隣接権・支分権の違い
音楽や映像には、3つの重要な権利があります。それぞれの対象と内容を理解しておきましょう。
- 著作権
音楽を作った作詞者や作曲者が持つ権利です。作品の内容を管理し、使用を許可する役割を持ちます。
- 著作隣接権
楽曲を演奏したアーティストや録音したレコード会社に与えられる権利です。音源そのものに関係しています。
- 支分権
著作権や著作隣接権をさらに細かく分けた権利です。
支分権は、利用方法ごとに分かれており、音楽を演奏するための「演奏権」や、音楽をコピーするための「複製権」など、さまざまな権利が存在します。
結婚式で音楽や映像を使う際には、それぞれの権利を理解し、適切に対応することが大切です。
▼関連記事はこちら▼
私的使用と営利的目的の境界線
結婚式で音楽や映像を使用する際には、著作権における「私的使用」と「営利的目的」の違いを正しく理解することが大切です。
「私的使用」とは、家族や友人などの限られた範囲で、個人的に音楽や映像を楽しむことを指します。
この場合、著作権者の許可を得る必要はありません。
一方で、結婚式のようなイベントでは、会場使用料やゲストへのサービス提供といった費用が発生するため、音楽や映像の使用が「営利的目的」とみなされます。
営利的目的で音楽や映像を使用する場合には、必ず著作権者の許可を得る必要があります。
結婚式でBGMや映像を無断で使用した場合、著作権侵害として法的責任を問われる可能性があるため注意が必要です。
適切な手続きを行い、必要な許諾を得てから使用するようにしましょう。
音楽利用における具体的なリスク
結婚式で音楽を使用する際、著作権に関するリスクを避けるためには、どのような利用が問題になるのかを理解しておくことが大切です。著作権を侵害した場合、次のようなリスクが考えられます。
まず、著作権者から音楽の使用停止を求められる可能性があります。
結婚式の最中に問題が発生すれば、式の進行に影響を及ぼすこともあるでしょう。
また、著作権侵害によって得た利益をもとに損害賠償が請求されることもあります。
さらに、著作権侵害は場合によって刑事罰の対象となります。
悪質な侵害と判断された場合には、 が科される可能性もあります。
これらのリスクを回避するためには、音楽を使用する前に必ず著作権者から適切な許可を得ることが必要です。
BGMとしての利用
結婚式のBGMを使用する際には、著作権の「演奏権」が関係します。そのため、使用には利用許諾が必要です。
しかし、ほとんどの結婚式場はJASRACと包括契約を結んでおり、その場合、JASRACが管理する楽曲CDは個別の申請をしなくても使用が許可されています。
ただし、すべての結婚式場がJASRACと契約を結んでいるわけではないため、事前に会場に確認しておくことが大切です。
また、結婚式で使用する音楽は市販されているCDを用意する必要があります。スマートフォンやCD-ROMにコピーした音楽は使用できないため、この点をしっかり把握し、適切な手続きを踏むことが求められます。
生演奏やDJパフォーマンス
結婚式でバンドやDJによる生演奏を行う場合、BGMと同様に著作権の「演奏権」が関係します。多くの結婚式場は、ASRACなどの著作権管理団体と契約を結んでおり、その場合、特別な手続きを行うことなく演奏が許可されています。
しかし、すべての式場が著作権管理団体と契約しているわけではないため、契約がない場合には別途許可を取得する必要があります。
映像作品への音楽の使用
結婚式で作成するプロフィールムービーやその他の映像に音楽を使用する場合、音楽をコピーする行為が「複製権」に該当します。
このため、音楽の著作権者であるJASRACだけでなく、音楽の原盤を管理しているレコード会社からも許可を得る必要があります。
個人で手続きを行うのは難しいため、専門の代行業者に依頼するのが一般的です。
著作権侵害の注意点
ほとんどの「作品」と呼ばれるものは著作権で保護されています。
JASRACなどの著作権管理団体に登録されていない楽曲でも、その作品が著作権で保護されている可能性があります。
そのため、使用したい作品が著作権法で保護されているかどうかを確認することが重要です。
以下の条件に該当し、保護期間内(著作者の死後70年まで))の作品は、使用するために許諾が必要です。
・日本人が作成したもの
・国内で初めて発行されたもの
・条約で日本が保護義務を負うもの
各ジャンルには専用の窓口が設けられていることが多いため、必要に応じて問い合わせて確認しましょう。
また、著作権とは別に「著作者人格権」にも配慮が必要です。
著作者人格権は、著作物の創作者が作品に対して持つ名誉や人格的利益を保護するための権利で、譲渡できません。
無断で公開や改変を行うと、著作者人格権の侵害となるリスクがあります。
このため、事前に契約で不行使を取り決めるなど、対策を講じておくことが求められます。
著作権侵害を防ぐための具体的な対応方法
著作権侵害を防ぐためには、普段の業務のなかで著作権に関するルールを意識し、具体的な対策を取ることが重要です。
著作権管理団体との契約の見直し
企業が著作物を利用する際、多くの場合はJASRACなどの著作権管理団体と契約を結んでいます。
ただし、契約内容がどこまでカバーされているのかを確認することが非常に重要です。
契約が不十分であると、知らぬ間に著作権侵害をしてしまう可能性があります。
とくに、新しい著作物を利用する際には、個別の許諾が必要かどうかを事前にチェックしましょう。
従業員の教育
従業員が著作権を正しく理解していないと、インターネット上の画像や音楽を無断で使用してしまうなど、知らずに著作権侵害をしてしまう可能性があります。
これを防ぐためには、社内で著作権に関する研修を実施し、基本的なルールや違反事例を共有することが重要です。
また、著作権侵害を防ぐための実務的な対応方法や、万が一の違反時の対応についても周知することが大切です。
権利処理の確立
著作物を利用する際には、その権利を確認し、必要であれば著作権者から適切な許可を得る仕組みを整えることが重要です。とくに、権利処理を担当する人を社内で決めておくと、スムーズに対応できます。
また、どの作品が許諾済みであるかを管理するためのリストやツールを導入することもおすすめです。
代替策の検討
著作権を侵害しないためには、代替策を検討するのも有効です。
たとえば、フリー音源には使用条件が明記されていることが多いため、利用規約を守るだけでリスクを回避できます。
また、ブライダル事業者が作詞・作曲したオリジナル楽曲を使用するのもひとつの方法です。
オリジナル楽曲を従業員自ら演奏する場合、特別な手続きは必要なく、著作権侵害を避けられます
弁護士に相談
権利関係が複雑な場合や、他社から著作権侵害を指摘された場合は、著作権に詳しい弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
とくに、複雑な権利が絡む作品を使用する際には、早期に相談することで大きなトラブルを未然に防げるでしょう。
リフト法律事務所のサポート内容
アートや映像作品、書籍など、あらゆる創作物は著作権法により保護されています。
結婚式で音楽を使用する際、とくに重要なのは「演奏権」と「複製権」という権利です。
これらの権利を無視して著作権を侵害した場合、損害賠償や刑罰を受ける可能性があり、企業の信頼にも大きな影響を及ぼします。
リフト法律事務所では、ブライダル業界向けの法務サポートを提供しています。
契約書や規約のチェックだけでなく、新規事業の法的リスクの確認や、経営視点でのアドバイスなど、広範囲のサポートが可能です。
著作権や法務リスクでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
▼関連記事はこちら▼
ウェディング業のための口コミ対策!Google口コミの削除方法を弁護士が解説
フォトウエディング事業者になる前に知っておくべき基礎知識と市場規模
ブライダル事業者は要注意!消費者契約法に新設されたキャンセル料水準の説明義務とは?
ブライダル業のインスタマーケティングを最大化する弁護士活用法
弁護士 川村勝之
- 弁護士によるブライダル・ウエディング業界への法務サポート
- 労働時間管理の必要性は?ブライダル業界のトラブル例も紹介
- ブライダル業界のカスハラ対策!弁護士に相談する必要性とは
- ブライダル業界における著作権問題~結婚式での音楽利用~
- ブライダル業の景表法対策「好評につき延長」の使い方を解説
- ブライダル業のインスタマーケティングを最大化する弁護士活用法
- ブライダル事業者は要注意!消費者契約法に新設されたキャンセル料水準の説明義務とは?
- フォトレイトの口コミ対策!削除方法を弁護士が解説
- フォトウエディング事業者になる前に知っておくべき基礎知識と市場規模
- ウェディング業のための口コミ対策!Google口コミの削除方法を弁護士が解説
- インボイスとは?ブライダル事業者が取るべき対策を解説
- Instagramで誹謗中傷?悪質な書込みへの対応を弁護士が解説
- 【弁護士が解説】フォトウエディング・前撮りで法律に注意すべき3つのシチュエーション
- 【弁護士が解説!】フォトウエディングの著作権で押さえるべき2つのポイント
- 【ブライダル業者必見!】婚礼写真に関する法律問題の注意点を弁護士が徹底解説
- 【ブライダル業者必見!】ブライダルと法律に関する押さえておきたいポイント3選と注意点を解説